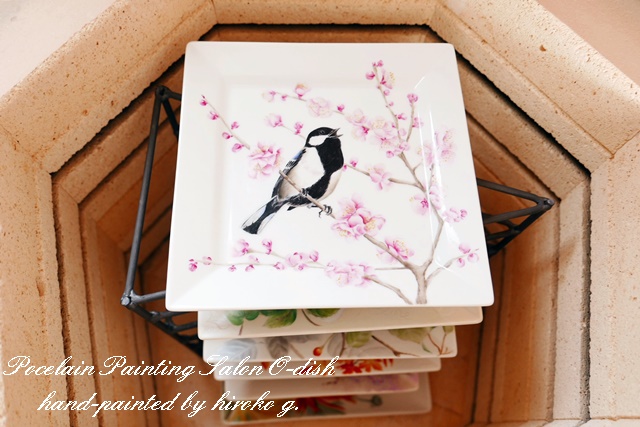 【電気炉】について続けて3記事目になります。今回は、ポーセリンペインティング上絵付けや転写紙を使った作品を焼く場合の焼成過程や温度について。
【電気炉】について続けて3記事目になります。今回は、ポーセリンペインティング上絵付けや転写紙を使った作品を焼く場合の焼成過程や温度について。
電気炉の種類も多様化し、使える設定などの違いがあるかもしれませんが、気をつけたい注意事項や各素材別の焼成温度については、共通するものとふまえ、焼成の手順をお伝えしていきます。
目次
焼成手順
上絵付けやポーセラーツ転写紙を使った作品を焼成するときの焼成過程
step
1窯詰め
白磁と白磁の間は約1cm弱は空けよう。焼成中の白磁は少し膨張する場合もあるので、あまりにも詰め詰めにはせず、ゆとりをもって並べる方が熱周りも良い。
step
2温度設定
マイコンで自動設定の窯もあるかもしれませんが、通常は使用した上絵の具の色、焼成回数によって変えて設定します。
例・・1回目の上絵付けとして【800℃】設定 キープ(練らし時間)【20分】など、【温度】と【キープ】の2つの数字を設定してスタート。
step
3ガス抜き
スタートしてから400~450℃になるまでは、電気炉の扉を半開きにして溶剤や金液に含まれる油煙を逃がす。
step
4電気炉の扉を閉める
400℃以上になってガス抜きが出来たら、忘れず扉を閉める。うちの窯の場合はスイッチを入れてから約1時間半ほどで閉めます。
step
5高温焼成・キープ・終了
扉を閉めた後は電気炉まかせで大丈夫。
step
6窯出し
白磁によっては温度差(季節による)で亀裂が入ることもあるので、100℃以下になっていても扉は開けず、できればお風呂の温度くらい(40℃台)まで待って開ける方が無難です。
電気炉の種類や窯詰めの量、または季節により、焼成にかかる時間や温度が下がるまでの時間は違ってくると思いますが、私のいつもの焼成過程では、窯入れから窯出しまでがだいたい12時間ほど必要。ですので夜に窯入れをして、就寝前に扉を閉めて、翌日に窯出しをするというサイクルです。
焼成過程での注意
ガス抜き
とても大切です。特に油性メディウム+絵の具、金彩、転写紙を使った時は、電気炉の扉を半開きやのぞき栓を開けておきます。この作業をしなかったら、作品表面がざらついたりします。
450℃前後で扉を閉めるのを忘れずに。扉を閉め忘れても焼成は続きますが、それでも作品表面がざらつく場合があります。
特に、金彩部分が多い作品を焼成しているときは、体に悪いと感じるにおいが充満します。私はいつも息を止めて目を細めて扉を閉めに行きます。
焼成中は窓を開ける、空気清浄機をつける、などにおい対策も必要です。
キープ設定
設定した最終温度を保つ時間のことを【キープ】や【ねらし】と言います。上絵付けでは20分前後で十分かと思います。キープ時間をかけることで上絵の具に含まれる鉛は安定してガラス被膜を生成し、その溶出のリスクは少なくなります。
絵付け後の金彩のみで焼成する場合はキープ時間は【0分】無しにしても問題ないです。
焼成スピード
電気炉により、設定できたりできなかったりするようですが、うちの窯は一応できます。でも毎回いちばん早いスピードの【5】に設定しています。
作品を炉内いっぱいに詰め込み過ぎると、熱周りが悪くなるので、スピードをゆっくりめにするなどされた方が良い場合もあります。私の場合は、たいていすかすかで焼成するので、スピードはMaxでしています。
焼成回数とともに温度も下げる
820℃はじまり→800℃→780℃など。回数ごとに温度は落としていくものです。が、2回で終わるような絵付けの場合でしたら、続けて同じ800℃とかでも問題ないです。
焼成回数の多くなりそうな、複雑なテクニックや特殊溶剤を使う場合は、計画的に絵付けと焼成段階を考慮して出来るだけ少ない回数で仕上げたいものです。
焼成回数が増えすぎると、絵の具の色や厚みによっては剥離や、変色が起こることも考えられます。白磁器自体は、よっぽどでないかぎり焼成しすぎたから割れる、というようなことはほぼありません。
焼成温度について
| 上絵の具 | 750~780℃ | 鉄赤系 |
| 800~820℃ | マロンなど含金系 | |
| 780~800℃ | いろんな色を使った時 | |
| 金彩 | 750~800℃ | 白磁に直接金彩した時 |
| 650~700℃ | 絵付け焼成後の金彩 | |
| 金下盛り・金下マット | 750~800℃ |
白磁に直接した時 |
| ラスター | 760~800℃ | 白磁に直接ラスターした時 |
| チッピングオフ | 780~800℃ | 白磁に直接釉薬剥離剤をつけた時 |
| ガラスビーズ | 740~760℃ | 絵付け焼成後に付けるビーズ |
| ガラス絵付け | 570~600℃ | 一般的なソーダガラスの場合 |
| 白磁転写紙 | 800℃前後 | 白磁の上に直接の時 |
| ガラス転写紙 | 520~560℃ | 一般的なソーダガラスの場合 |
上絵付けの焼成温度
ピンク系やマロンなど、含金系バイオレットやブル―を使った第一焼成であれば最初から820℃で良いと思います。

しかし、絵付けはたいてい赤だけ、マロンだけという単色で描いて、それだけを焼成するということは少なく、いろんな色を使って焼成することが多いかと思います。ですので、焼成温度で一番多く設定する温度は780~800℃です。
鉄系の赤や茶、イエローブラウンを使う場合は、第二焼成以降に使うようにするなど、発色良い仕上がりになるよう計画を立てて焼成しましょう。

色々な技法を使った時の焼成温度

- ① ラスター
- ② 極小ビーズ
- ③ チッピングオフ
- ④ ビーズ玉
上の写真のように一つの皿の上に特殊技法てんこ盛りの時は、焼成温度を迷いがちですが、780℃で何度か焼成しても大丈夫です。
ガラスビーズ類は、焼成温度がいちばん低いので、最後の最後に仕上げよう。
また、第二焼成以降の作品や、金下盛りをした作品、特殊溶剤(ラスターやチッピングオフなど)いろいろなジャンルのものを同じ窯で焼きたい場合もよくあり、そんな時も780℃が使い勝手よい温度です。
上記写真の特殊溶剤を用いた作品作りについては下↓のリンクよりご覧いただけます。
-

-
カキツバタ上絵付け皿に【特殊溶剤】を使った作品制作工程
ひとつのお皿に特殊技法をいろいろ盛り込んだ作品の紹介です。初めて使う溶剤などは、どのような仕上がり具合になるのか、まずは本番でない作品で事前に実験してみることをおすすめします。 焼成後の ...
続きを見る
焼成温度についてのまとめ

焼成の手順や過程、各種焼成温度などについて書いてみました。すでに焼成経験のある方は、少し違うかも!?と感じられた方もいらっしゃるかもしれません。電気炉の種類によりけりでもあるので、お手持ちの説明書を一番の参考にされてくださいね。私の窯は古いので、何度か引っ越しもしたりで説明書をずいぶん前に紛失してしまいました。
まだこれから電気炉を購入しようかとお考えの方は、何やら手順が面倒くさそう、難しそうと感じられたかもしれませんが、要は説明書をよく読み電化製品と割り切って使いこなすだけです。
聞いた話で、たくさん焼成する方は、焼成終了後100℃をきったらすぐ開けて、温度が下がらないうちに、次の作品に入れ替える…ということですが、火傷しないように気を付けて、冬など気温差があるときは、100℃をきってもあまり早く窯のふたを開けない方がよいかと思います。
100℃はずっと下回っていたけれど、常温になる前にふたを開けて軍手をして取り出していたら、軍手が焼き縮んで!?穴が開いたことがありました(笑) また、やはり外気と温度差があったためか、取り出した作品の端が少しの接触でかけてしまったことがありました。100℃をきっても作品は熱々ですから、取り出すときは慎重にしなければいけません。色々と失敗を重ねると無理をしないでおこうという気持ちになります。
-

-
上絵付けやポーセラーツで使う【電気炉】について①
焼成しないと仕上がらない絵付けやポーセラーツにおいて、必要不可欠な高価なお道具が【電気炉】です。現在はいろいろなメーカーから多種の電気炉が販売されているので、使用法や使い心地は一概には言えませんが、私 ...
続きを見る
-

-
【電気炉】を使う前の準備と焼成の失敗や注意点について②
初焼成前の準備 無事に電気炉の設置を終えたら、初焼成前の準備をします。付属の説明書にも記載されていることですが、棚板(作品をのせる板)にアルミナ粉を水である程度溶いて、刷毛で添付し、十分に天日干しをし ...
続きを見る